
目 次
はじめに
公務員として働きながら副業でブログを運営し、収益を得ることはできるのでしょうか。本記事では国家公務員・地方公務員がブログ収益化を行う際の合法性や注意点について、法律(国家公務員法・地方公務員法等)の根拠を踏まえて解説します。公務員でも可能な副業の種類、ブログ運営が違法となるケース、アフィリエイト掲載の可否、ブログを始める前の準備や運営時の注意事項まで、8つの観点でまとめました。
公務員の方が安心して副業ブログに挑戦できる知識を提供します。

公務員ってブログ運営していいの??
☑︎公務員として副業を検討している方
☑︎公務員としてブログ運営を検討している方
☑︎公務員としてブログ運営の違法の可否を知りたい方
☑︎すでに公務員としてブログ運営をしている方
結論(国家公務員・地方公務員のブログ収益化の合法性概要)
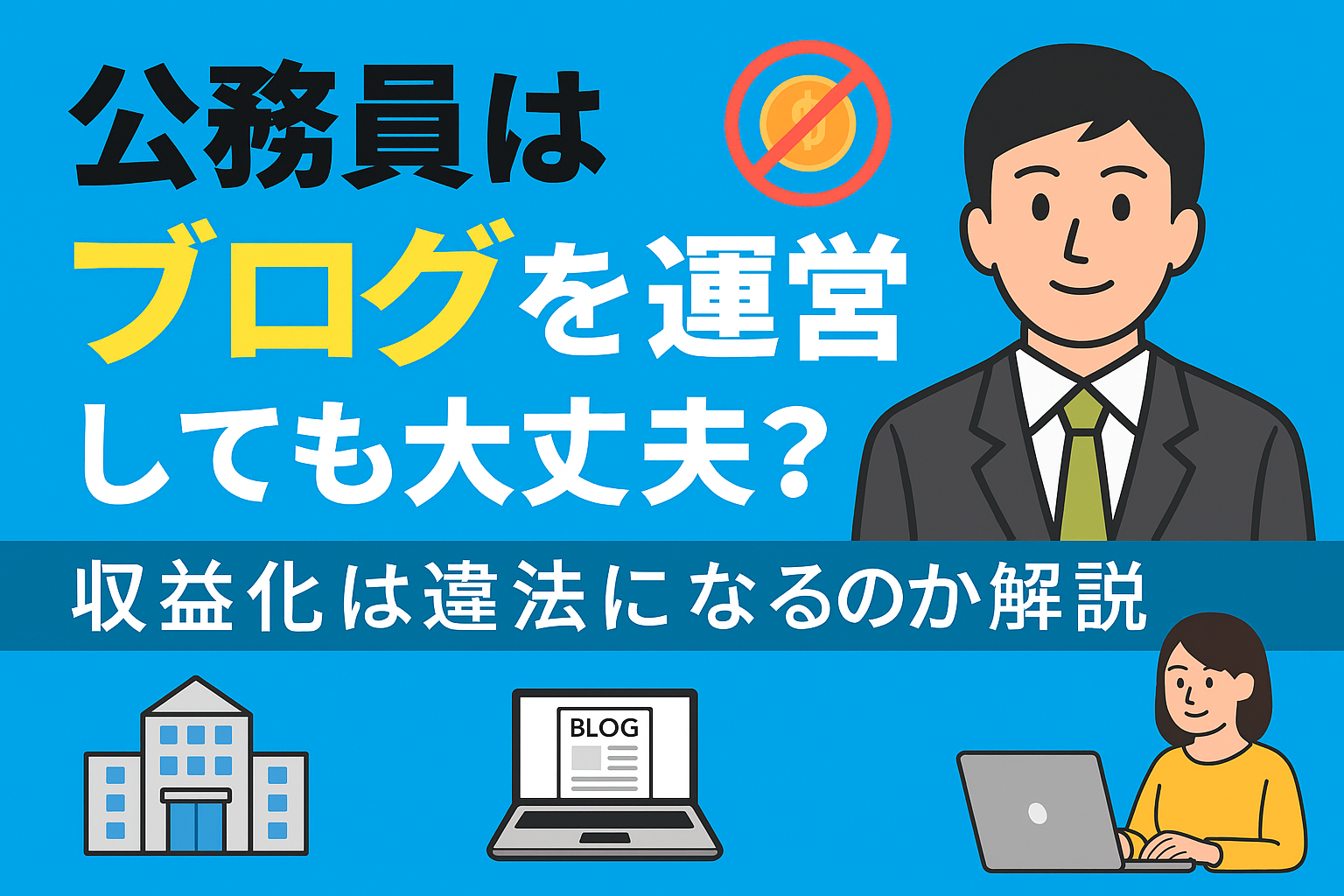
まず結論として、公務員がブログで収益化する行為は原則として法律で禁止された副業に該当します。国家公務員法第103条・104条および地方公務員法第38条により、公務員は営利企業の経営や報酬を得る副業が制限されています。ブログに広告収入やアフィリエイト収入を得ることは「報酬を得る継続的な事業」に当たるため法律上はグレーではあるものの基本的には禁止行為と解されます。実際、明確に違法と断定できるかについては議論がありますが、公務員の副業禁止規定が適用される可能性が高く、高リスクであることは否めません。
ただし、後述するように一部の自治体では副業解禁の動きもあり、条件付きで許可されるケースや黙認されている実態もあります。総じて、国家公務員は許可なくブログ収益化することはほぼ不可、地方公務員も所属先の許可がなければ違法リスクが高いと言えます。
公務員ができる副業リスト(法律上認められているもの)

公務員でも法律上認められる(または許可を得やすい)副業には以下のようなものがあります。
- 不動産収入: 小規模な不動産賃貸による家賃収入は認められます(例: 戸建て5棟未満かつ10室未満、年間収入500万円未満等)。一定の条件を満たす範囲であれば資産運用としての不動産貸付は可能です。
- 株式・投資: 株式・FX・暗号資産などへの投資による利益は副業ではなく資産運用と見なされ、自由に行えます(※勤務時間中に取引しない、インサイダー取引をしない等の注意は必要)。
- 講演・執筆: 一回限りの講演や執筆で得る謝金は、許可なく受け取れる場合があります。継続的な執筆連載などは申請・許可が必要ですが、単発の講演や著書出版などは認められることが多いです。
- 小規模な農業: 自家消費目的の小規模農業は兼業が認められています。地域によってはある程度規模が大きくても許可されている例があります。
- 家業の手伝い: 家族経営の事業を無報酬で手伝うことは問題ありません。報酬が発生する場合でも親族名義の事業であれば許可を得られる可能性があります。
これら以外にも、自治体によってボランティア活動や地域貢献に資する非常勤の仕事など、公益性が高く本務に支障のない活動は許可されるケースがあります。
ブログ運営が違法となるケース(国家公務員・地方公務員別)
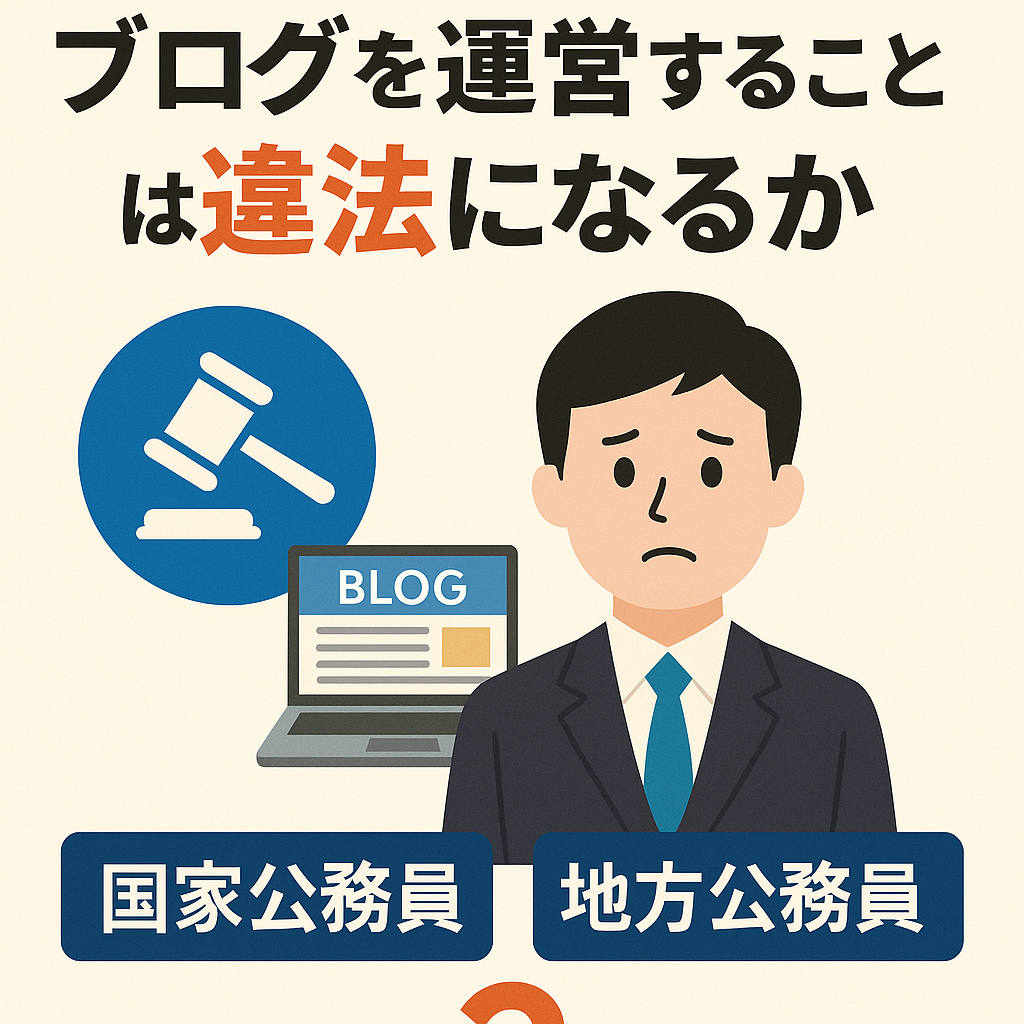
公務員がブログ収益化で違法と判断される主なケースは次のとおりです。
- 許可のない営利活動: 国家公務員が人事院の承認なく広告収入目的でブログ運営すること、地方公務員が任命権者の許可なく営利目的でブログ収益を得ることは、副業禁止規定に抵触します。とくに国家公務員は法律上副業許可の制度が極めて限定的であり、許可なく収益化すれば違法と見なされます。地方公務員も許可なく継続的な収益を得れば地方公務員法違反です。
- 職務専念義務違反: 勤務時間中に記事執筆やサイト管理を行った場合、職務専念義務(地方公務員法第35条等)に反し懲戒処分の対象です。勤務時間外に限定するのは大前提となります。
- 職務上知り得た情報の公開: ブログ内容に公務で得た非公開情報や内部事情を記載すると、守秘義務違反(国家公務員法第100条・地方公務員法第34条)となり違法です。たとえ副業でなくても機密漏洩は重大な処分事由です。
- 信用失墜行為: 公務員の品位を損なうような不適切な内容(差別的発言や違法な内容の発信など)をブログに掲載すると、信用失墜行為の禁止規定(国家公務員法第99条・地方公務員法第33条)に抵触します。収益化以前の問題として懲戒対象となり得ます。
- 利益相反となる場合: 自分の職務分野に関連する商品・サービスをブログで宣伝し利益を得ると、職務上の利益相反や公平性の疑念を生じます。例えば、規制業務を担当する公務員が関連業界の商品をアフィリエイト紹介することは不適切で、発覚すれば処分につながるでしょう。
なお、「違法と断定はできないグレーゾーン」との指摘もあるように、公務員のブログ収益については厳密には判例がなく解釈が分かれる部分もあります。しかし過去には自衛隊員がYouTubeで広告収入を得て懲戒処分を受けた例や地方公務員が無許可副業で停職処分となった例も報道されています。処分例が皆無ではない以上、「黙認されているから大丈夫」と安易に考えるのは危険です。
アフィリエイト掲載の法的問題(合法となるケースと注意点)

アフィリエイト広告をブログに掲載することも、基本的には「営利目的の副業」と見なされるため、公務員には厳しい制約があります。広告リンクを貼って成果報酬を得る行為は、法律上は広告収入と同様に扱われます。
- 合法となり得るケース: 公務員が趣味のブログにたまたまアフィリエイトリンクを貼る程度で、収益がほとんど発生しない場合は実質的に黙認される可能性があります。「営利を目的としない情報発信で、結果として僅かな報酬が出た」という建前であれば、厳密には副業と断じにくいグレーと言えます。とはいえ形式上は報酬を得ている以上、所属機関が問題視すれば違法解釈されうることを忘れてはいけません。
- 許可を得た場合: 地方公務員で所属長の許可を正式に得られれば、規定上はアフィリエイト収入も容認されます。しかし実際には、公務員が営利広告収入のためのブログ運営を申請しても許可が下りる例は極めて稀でしょう。どうしても副業ブログをしたいなら、事前に上司と相談し許可を求める価値はありますが、認められる可能性は低いと考えましょう。
- 注意点(掲載に当たって): 仮にアフィリエイトを行う場合、勤務時間外に限定し職場のPCやネットワークは使わないこと、公務と無関係の分野に留めることが重要です。また「公務員の立場」を売りにしない(公務員であることを明かさない)こともトラブル防止になります。収入が出た場合は適切に確定申告を行い、住民税から職場に副業が発覚するリスクにも備える必要があります。広告主との契約内容にもよりますが、公務員倫理規程に反するような利得供与と受け取られないよう留意してください。
要するに、アフィリエイト掲載は法的には副業禁止の範囲であり、「完全に合法」と胸を張って言えるケースは限られます。不用意に始めれば懲戒のリスクがある点を十分認識してください。
公務員がブログを始めるためにやるべき準備(届け出、匿名性など)

公務員がリスクを抑えてブログを始めるなら、以下の準備を万全に行いましょう。
- 所属機関への確認・届出: まず職場の就業規則や服務規程を確認し、副業に関する内規がないか調べます。その上で可能であれば上司に相談し、「業務外の趣味ブログを開設したいが問題ないか」打診してみましょう。正式な兼業許可申請まではしなくとも、事前に相談記録を残しておくことで万一発覚した際の心証が違います。地方公務員の場合、副業届出や許可申請の制度が用意されている自治体もありますので、規程に従い手続きを検討してください。
- 匿名での運営: ブログは必ず匿名(ペンネーム)で開設し、本名・勤務先が特定されないようにします。ドメイン登録者情報も代理公開サービスを利用するなど、身バレ防止策を講じてください。SNS連携する場合も、公務員であることや個人を特定できる情報は一切出さないよう注意します。
- 収益化しない選択肢: 収入が発生しなければ厳密には副業ではありません。まずは広告を貼らずに情報発信だけ行い、趣味ブログとして様子を見るのも賢明です。ブログ運営に慣れ、副業解禁の流れが進むのを待ってから収益化するという段階的アプローチも一案です。
- 情報発信のテーマ選定: 公務と利害関係のないテーマを選びましょう。職務関連の専門知識を発信したい場合でも、役所の看板を背負った内容と受け取られない工夫(個人の意見との断り書き等)が必要です。趣味・生活・技術系など職務と交わらない分野で始める方が無難です。
これらの準備をすることで、万一ブログ運営が発覚した場合でも「善意でルールを守ろうと努めていた」ことを示すことができます。何も考えず始めるより格段にリスクを減らせるでしょう。
運営上の注意点(勤務時間外か否か、公務との利害関係、コンテンツ内容など)

実際に公務員がブログを運営する際は、以下のポイントに十分留意してください。
- 勤務時間外に限定: ブログ執筆・更新作業は必ず勤務時間外に行います。職場のPCやWi-Fiを使うのも厳禁です。ログ等から勤務中の更新が発覚すると、それだけで処分対象になり得ます。休憩時間でも職場設備での更新は避け、自宅のPC・スマホから夜間や休日に作業しましょう。
- 職務に影響を及ぼさない: ブログ活動が原因で本業に支障が出てはいけません。寝不足で業務に支障が出たり、取材・執筆のために休暇を乱用することのないよう自己管理が必要です。「公務専念義務を果たした上で趣味としてやっている」という建前を崩さないようにします。
- 利害関係の回避: 公務と利害関係が生じる内容は扱わないようにします。自分の勤務先や管轄地域に関連する話題、業務上関わる企業の商品レビューなどは避けましょう。利益相反や公平性の疑念を持たれると、たとえ副業でなくても問題視されます。
- コンテンツ内容の配慮: ブログ記事は公序良俗に反する内容や過激すぎる表現を避けます。公務員の信用を失墜させないよう、節度ある発信を心掛けてください(法律や制度への批判を書く際も言葉遣いに注意)。また読者から公務員であることを見破られないよう、身辺に関する記述にも気を付けます。身バレしそうなエピソードや写真の掲載は避けましょう。
- 収入の管理: 万一収益が出た場合は確定申告を適切に行います。住民税の納付方法に配慮し、副業分を自分で納付(普通徴収)にすることも検討してください。収入額が大きくなりすぎると周囲の目につきやすくなるため、程々のところで抑えることもリスク管理になります。
最後に、「バレないように極力工夫する」ことが大切です。周囲の同僚にも副業ブログのことは決して口外せず、SNSでもリアルの知人に知らせないよう徹底しましょう。副業ブログはグレーとはいえ、慎重に運営することで余計なトラブルや嫉妬を招かずに済みます。
まとめ
公務員のブログ収益化について、法律上は原則禁止でありリスクが高いという結論になります。国家公務員・地方公務員ともに営利目的の副業は禁止されており、ブログの広告収入やアフィリエイトもその例外ではありません。ただ、実際にはグレーゾーンとされる側面もあり、多くの公務員ブロガーが匿名で活動している現状もあります。もし公務員がブログを収益化したい場合は、
- 法律と職場規程を把握し、可能であれば上司に相談すること
- 勤務時間外・匿名で慎重に運営し、職務への影響を絶対に出さないこと
- 許可される副業と許可されない副業の線引きを理解すること
が重要です。最終的には自己責任となりますが、本記事で挙げた知識と対策を踏まえて行動すれば、リスクを減らしつつ情報発信を行えるでしょう。公務員としての本分を全うしながら、上手に副収入を得る道を模索してみてください。法律の範囲内で創意工夫し、ぜひ安全第一でブログ運営を始めてみましょう。
参考資料: 国家公務員法(第103条・104条)、地方公務員法(第38条)、公務員の副業に関する総務省通知、公務員の副業解禁に関するニュース記事など。


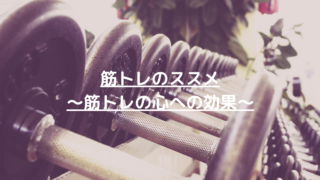


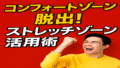
コメント