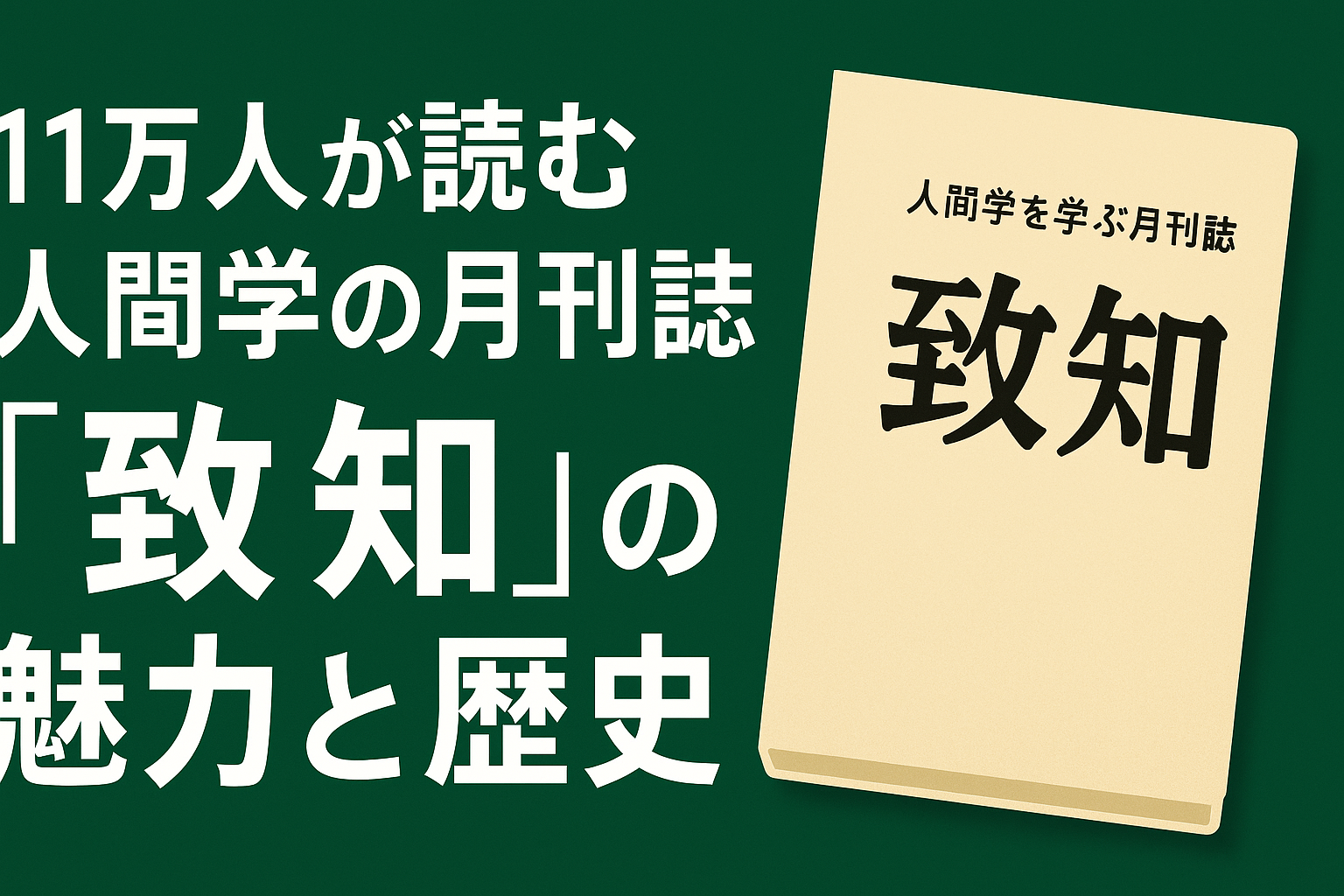
目 次
はじめに
月刊誌『到知』をご存じでしょうか。『到知』は、人間としての生き方や学びを深める「人間学」に焦点を当てたユニークな雑誌です。創刊以来約半世紀にわたり、有名無名を問わず各界の一流人物の体験談や哲学を紹介し、読者の心に響く教えを届けてきました。本記事では、『到知』という雑誌がどのように成り立ち、どんな人々に読まれているのか、そしてそこから何を学べるのかを詳しく解説します。自己啓発やリーダーシップに関心がある方、生き方の指針を求める方はぜひ読み進めてみてください。

こんな本の存在知らなかった、、
☑︎人間的成長を求める社会人の方
☑︎若手リーダー・管理職の方
☑︎生き方・人生哲学に関心がある方の方
到知とはどういう本か(雑誌の成り立ち・歴史・編集方針)
『到知』(致知)は1978年9月に創刊された月刊誌で、「日本で唯一の人間学を学ぶ月刊誌」です。発行元は致知出版社で、発行者(創刊者)は藤尾秀昭氏が務めています。創刊当初から**「いつの時代でも仕事にも人生にも真剣に取り組んでいる人はいる。そういう人たちの心の糧になる雑誌を創ろう」**という創刊理念が掲げられ、書店では販売せず定期購読制ながら口コミで愛読者を増やしてきました。実際、創刊から47年を経た現在でも約11万人に定期購読されており、発売以来一号も休まず発行が続けられています。
『到知』の誌名には深い意味があります。東洋の古典『大学』の一節「格物致知(かくぶつちち)」に由来しており、「実践を通して本物の知恵を身につける」という思いが込められています。現代は知識や情報があふれていますが、頭で理解しただけの知識は真の役には立たない――体験によって初めて知識が生きる力となる、という考えから名付けられました。つまり経験に裏打ちされた知恵(Wisdom)を重視する編集方針を象徴する名前なのです。
編集方針としては**「一流の人たちの生き方に学ぶ」ことを貫いており、創刊以来一貫して「特集主義」、すなわち毎号テーマを設けて多彩な分野の人物の生き様や教えを紹介しています。各号の特集テーマには「人生の四季をどう生きるか」「時代を拓く」「幸福の条件」など、古今東西の名言や徳目が掲げられ、深みのある内容が展開されます。たとえば2023年の号では毎月異なるテーマが組まれ、経営者や文化人、スポーツ選手など各界で一道を究めた人物の談話が掲載されました。こうした編集方針に基づき、有名無名を問わず各界各分野で道を切り開いてきた方々の貴重な体験談**を紹介することで、読者にとって仕事や人生の指針となる言葉や信条を届けています。
どんな層の人に読まれているか(読者層)
『到知』は一般的な書店では手に入らないにもかかわらず、読者の口コミによって着実に広まり、現在では定期購読者が11万人を超えています。読者層は経営者や管理職などビジネスリーダー層が多いことで知られますが、それだけではありません。企業経営者から若手社会人、学生に至るまで幅広い世代・職業の人々に愛読されているのが特徴です。実際、『到知』読者の有志による若者勉強会「致知若獅子の会」には10代・20代から30代半ばまでのビジネスマン、教師、経営者、学生など様々な立場の若者が参加し、互いに切磋琢磨しています。このように次世代の若者からベテランまで多くの人々が、自らの人格や生き方を高めるヒントを求めて『到知』を手に取っているのです。
著名人の中にも『到知』の愛読者が多数います。たとえばプロ野球界のレジェンドである王貞治氏(福岡ソフトバンクホークス球団会長)は長年『致知』を読み続け、「人の生き方に学ぶことの大切さ」を教えられてきたと述べています。またノーベル賞受賞科学者の大村智氏(北里大学特別栄誉教授)は「自分の生き方はこの雑誌の影響を色濃く受けている」と語り、茶道裏千家前家元の千玄室氏も「毎号『致知』を読むことで人間を学ぶ意義をしみじみ感じる」と評価しています。スポーツ界では元プロテニス選手の松岡修造氏が『致知』を「心を成長させてくれるなくてはならない存在」と評し、登場する先達から人間学を感じ取っているとコメントしています。このように各界のリーダーから支持されていることも、『到知』の信頼性と価値を物語っています。
さらに、『到知』は単に個人で読むだけでなく企業内の研修教材としても活用されています。実際に「社内木鶏会(しゃないもっけいかい)」と称して、『致知』をテキストに社員同士で感想を発表し合う勉強会を導入する企業が増えており、現在国内外の1,350社以上で定期的に開催されています。社内木鶏会を通じて「社風が良くなった」「社員の一体感が高まった」などの声も寄せられており、組織の人材育成や理念共有のツールとしても『到知』が役立てられているのです。このことからも、『到知』が幅広い層に支持され、個人の自己啓発だけでなく組織づくりにも資する雑誌であることがわかります。
何を学べるのか(人間学、リーダーシップ、歴史人物の思想、人生哲学など)
『到知』最大の魅力は、読者が**人生に役立つ深い学び(人間学)**を得られる点にあります。では具体的に何が学べるのでしょうか。キーワードとなるのは「人間学」「リーダーシップ」「歴史人物の思想」「人生哲学」です。それぞれ詳しく見てみましょう。
- 人間学(人間力の涵養): 人間学とは「この唯一無二の命をどう生きるか」を探究する学問であり、自らの人格を高め豊かな人生を送るための智恵です。『到知』の記事を通じて、古今の偉人たちの教えや先達の生き様に触れることで、自分の内面を磨き人間力を養うことができます。歴史や古典から学ぶ教養も多く、たとえば論語や『菜根譚』といった東洋の教えが現代にどう生きるかを教えてくれる記事もあります。人間学を探究して45年という編集方針の下、**「自分にしか生きられない人生を豊かに生き抜く」**ためのヒントが詰まっているのです。
- リーダーシップ: ビジネスや組織運営におけるリーダーシップの知恵も『到知』から多く学べます。経営トップや指導者のインタビュー記事では、組織を率いる上での哲学や心得が語られています。たとえばファーストリテイリングCEOの柳井正氏は「運命をひらくリーダーの条件」について自身の経験を語り、日本電産創業者の永守重信氏は「経営者の器が企業を決める」という信念を示しています。スポーツの世界からは、柔道オリンピック金メダリスト野村忠宏氏が逆境を乗り越える心構えを語り、プロ野球監督の栗山英樹氏が「人として生きる上で必要なもの」を学び続ける姿勢を見せています。こうした具体例から、真のリーダーシップとは何か、組織を率いる者に求められる人間力とは何かを深く考えさせられるでしょう。
- 歴史人物の思想: 『到知』には歴史上の人物や偉人の思想・名言を紹介する記事も多く掲載されています。過去の特集テーマを見ても、「人生を導いてくれた古典の教え」(立命館APU学長・出口治明氏)や「武士道に学ぶ」など、歴史に培われた知恵を現代に生かす内容が取り上げられています。たとえば江戸時代の陽明学者・佐藤一斎の言葉「学を為す故に書を読む(学問を成すために書物を読む)」をテーマに、現代の教育者が対談する記事もありました。このように歴史的人物の思想や名言から、自身の生き方の指針を得ることができるのも『到知』の魅力です。先人の成功と失敗、信念や哲学に学ぶことで、現代の私たちも人生の指標となる「不易の真理」を見出せるでしょう。
- 人生哲学: 最後に挙げるのは人生哲学や人生訓です。『到知』には各界の人生の達人たちの哲学が凝縮されています。デザイナーのコシノジュンコ氏が「人生は常にこれから!」と語れば、歌舞伎俳優の坂東玉三郎氏は「歌舞伎一筋に生きて」きた信念を示し、将棋棋士の羽生善治氏は勝負の世界から得た「負けない生き方」の極意を説きます。さらには、教育者や医師、芸術家やスポーツ選手まで、それぞれの歩んだ人生から導き出された珠玉の人生訓が読者の胸に迫ります。読めば「こんな考え方があるのか」「こんな生き方もできるのか」と視野が広がり、自分の人生を見つめ直すきっかけになるでしょう。
実際、読者からは「『致知』で学んだことが血肉となり、自分の人生を形づくってくれた。最も勉強になる雑誌だ」という声も寄せられています。別の読者は「多忙な日々でも『致知』を読むと必ず鼓舞する言葉に出会え、心を整えられる」と述べています。このように、『到知』には単なる知識ではなく読む人の魂に響く人生の智恵が満載であり、それぞれの読者が自分なりの学びや気づきを得られる余地があるのです。
まとめ
月刊誌『到知』は、人間学という視点から人生をより良く生きるためのヒントを提供してくれる稀有な雑誌です。創刊から今日まで一貫した理念のもと、有名無名を問わず多くの先人たちの体験談と智慧を届けてきました。経営者をはじめ多くのリーダーたちが愛読し、若い世代からも支持されているのは、そこに普遍的で実践的な学びがあるからに他なりません。仕事や人生に悩んだとき、自分を高めたいと願うとき、『到知』を開けば先人の言葉がきっと心の指針となってくれるでしょう。ぜひ一度手に取って、人間学の世界に触れてみてください。それはきっとあなた自身の生き方を見つめ直し、磨き上げる大きなきっかけとなるはずです。


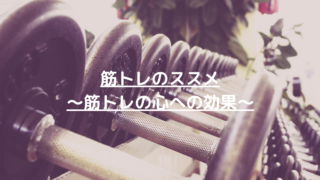


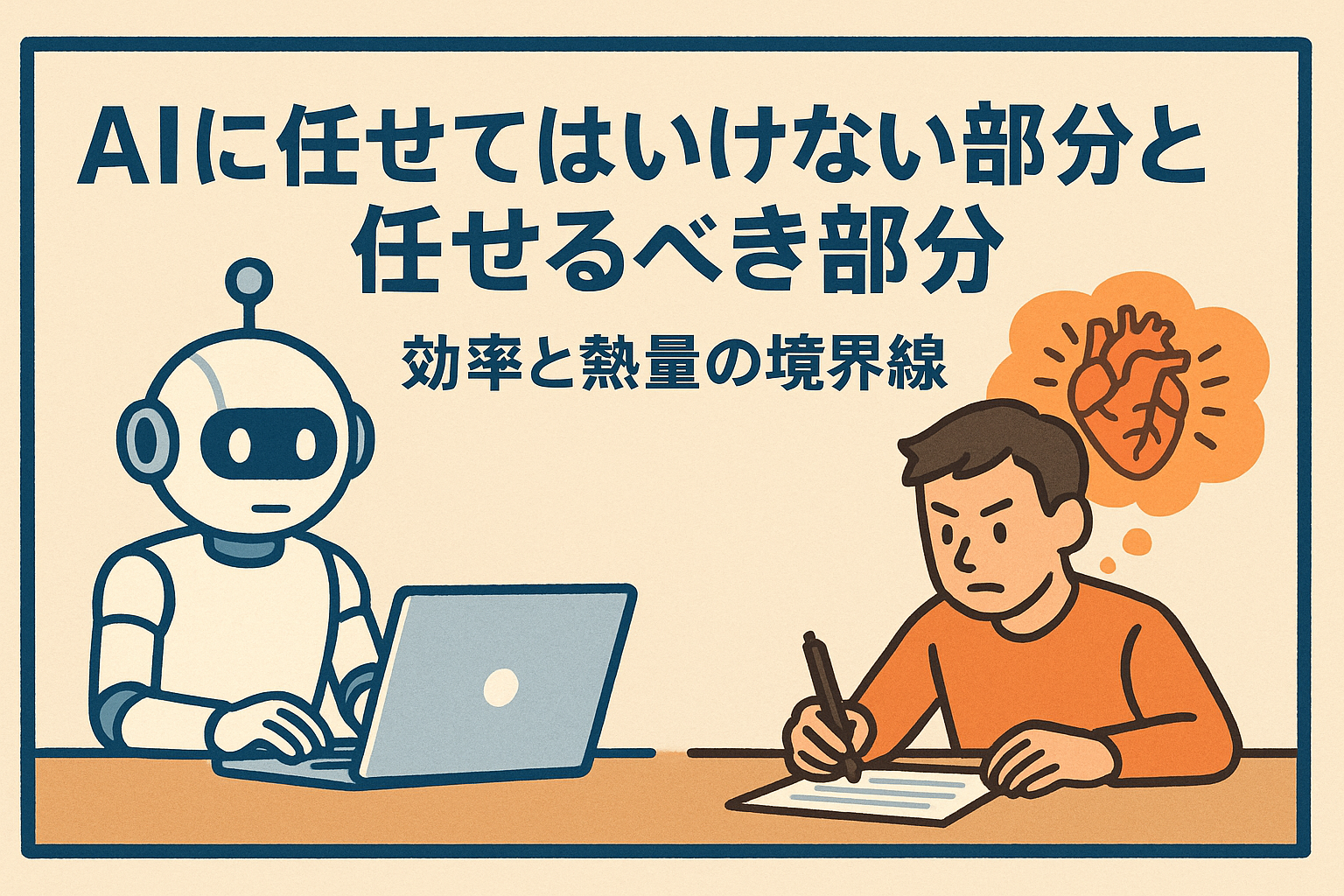
コメント