
① はじめに
現代のオフィスワークでは、一日中座りっぱなしで過ごす人がとても多いですよね。パソコンに向かって長時間作業していると、つい休憩を忘れてずっと座り続けてしまうものです。実は、この「座りすぎる生活習慣」こそが新たな健康リスクとして注目されています。長時間椅子に座り続けることは、体の不調を引き起こすだけでなく、心の健康にも悪影響を及ぼすことがわかってきました。
そこで本記事では、オフィスで働く全年齢層の皆さんに向けて、座りっぱなしが招く健康上のリスクと、今日からできる簡単な対策をご紹介します。健康維持のポイントやデスクワーク中でも実践できる工夫を、わかりやすくお伝えしますね。それでは早速始めましょう!

仕事中は座っていることが多いなぁ、、
☑︎デスクワーク中心の方
☑︎健康志向の方
☑︎仕事中にもできるリフレッシュ方法を知りたい方
② 座りっぱなしによる疾患のリスク

皆さんは、1日に何時間くらい座って過ごしていますか?実は日本人の平均座位時間は世界で最も長く、1日あたり7時間にも及ぶことが報告されています。この長時間の座りっぱなしが、喫煙や飲酒にも匹敵する深刻な健康リスクを高めるといわれているのです。具体的には、ずっと座り続ける生活は血流や筋肉の代謝を低下させ、肥満・糖尿病・心筋梗塞・脳卒中など様々な病気の危険性を高めます。さらに近年の研究では、長時間の座位が結腸がんや乳がんの発症リスクとも関連することが明らかになっています。ずっと座っていると脳への血流も悪くなり、将来的に認知症の一因となる可能性も指摘されているほどです。
「少しくらい座ってても平気でしょ?」と思うかもしれませんが、影響は侮れません。ある調査では、1日に11時間以上座っている人は、4時間未満の人に比べて死亡リスクが約40%も高まるという結果が報告されています。また別の研究では、**1日8時間以上座る人は3時間未満の人より死亡率が1.2倍(約20%増)**になるとのデータもあります。週末に少し運動する程度ではこの悪影響は打ち消せないとも言われており、日々の生活で長時間座り続けること自体が健康リスクとなるのです。世界保健機関(WHO)も2020年のガイドラインで初めて「座りすぎ」を健康を害する要因として明記し、世界で年間200万人もの死亡原因になっていると発表しました。これはもはや放っておけない問題ですよね。
では、なぜ座りっぱなしだと体に悪いのでしょうか?ポイントは筋肉と血行にあります。人間の下半身、特に太ももの筋肉は全身の筋肉の約70%を占めており、「第二の心臓」とも呼ばれる重要な役割を担っています。歩いたり立ったりと筋肉を動かすことで血液循環が促進され、糖や脂肪の代謝も活発になります。ところが、椅子に座りっぱなしで下半身を動かさない状態が続くと、筋肉がほとんど使われず代謝が落ちてしまいます。その結果、血糖値や血圧が上昇し、脂質異常や肥満につながってメタボリックシンドロームのリスクが高まるのです。メタボが進行すれば高血圧や糖尿病を招き、そこから心臓病や脳血管疾患など重大な病気につながる恐れもあります。つまり、ずっと座っている生活習慣は体の機能を低下させ、**「万病のもと」**になりかねないのです。
さらに、長時間のデスクワークで姿勢が固定されることによる不調も無視できません。例えば背中を丸めた姿勢や深く腰掛けた姿勢で何時間もいると、腰や首・肩の筋肉に負担がかかり続けてしまいます。日本人の訴える不調の上位には昔から腰痛や肩こりがありますが、実は椅子の性能が良くなった現代でも腰痛持ちや肩こりの人は一向に減っていません。座り心地が良くなったことでかえって長時間座りすぎてしまい、腰や肩への負担を蓄積させている可能性があります。どんなに良い姿勢であっても同じ姿勢を保ち続けること自体が体にとっては負担になる、というのは覚えておきたいポイントですね。
③ 座りっぱなしによるメンタルへのリスク

座りっぱなしの生活は、**心の健康(メンタルヘルス)**にも大きな影響を及ぼします。体を動かさずじっと座り続けていると気分転換ができず、脳の働きも低下してしまいがちです。その結果、ストレスや不安感が高まり、うつ病などメンタル不調のリスクが高くなることが指摘されています。実際、日本人を対象とした調査では、1日に12時間以上座っている人は6時間未満の人に比べて「心の健康状態が良くない人」の割合が約3倍も多いことが分かりました。長時間座っていることで生じる疲労感やストレス過多が、心の不調を引き起こしている可能性があります。オフィスで「なんだか憂うつだ」「集中力が続かない」と感じる日が多い方は、ひょっとすると座りっぱなしの生活習慣が影響しているかもしれません。
座りすぎによるメンタルヘルスへの悪影響としては、気分の落ち込み・イライラ感の増大・モチベーションの低下などが挙げられます。ずっと同じ姿勢で画面を見つめていると脳が刺激を受けにくくなり、リフレッシュされないため感情も沈みがちになります。特に仕事で強いストレスにさらされている状況下では、身体活動の不足がストレス解消の機会を奪ってしまい、不安症状や抑うつ症状が現れやすくなると考えられます。まさに**「心と体はつながっている」**ということで、体を動かさない生活は心にも悪影響が及ぶというわけですね。
では、メンタル面の不調を防ぐにはどうすれば良いのでしょうか。ポイントの一つは、適度に体を動かして気分転換を図ることです。日頃から軽い運動を取り入れることで、脳内で**「幸せホルモン」セロトニンが分泌され、ストレスを和らげる効果が期待できます。例えば有酸素運動**(ウォーキングや軽いジョギングなど)はセロトニン分泌を促し、気分を前向きにしてくれるとされています。オフィスワーク中でも、休憩時間に少し歩いたりストレッチをしたりするだけでリフレッシュ効果がありますよね。実際、「気分が落ち込んだときは体を動かすとスッキリした」と感じた経験がある方も多いのではないでしょうか。
もちろん、仕事が忙しくて運動する時間が取れない…という場合もありますよね。その場合でも大丈夫、次の章で紹介する簡単な対処法を生活に取り入れることで、心の負担をグッと軽くすることができます。大切なのは、「ずっと座りっぱなし」をできるだけ避けて、小まめに自分の心身をリセットする習慣をつけることです。メリハリをつけて体と心を休ませれば、仕事の効率も上がり一石二鳥ですよ。
④ オフィスでもできる具体的な処置・対策

座りっぱなしの悪影響を防ぐには、**「できるだけ長時間座り続けないこと」**が何よりの対策です。とはいえ、デスクワーク中心の仕事や運転業務などの場合、「座らないで仕事をする」のはなかなか難しいですよね。そこで大事になるのが、仕事の合間にこまめに立ち上がって体を動かす習慣を取り入れることです。海外では「30分ごとに2〜3分立ち上がって歩く」といった指針も提案されており、実際この程度の短い休憩でも座りすぎによる健康リスクを軽減できると言われています。オフィスでも少し意識するだけで実践できる工夫はたくさんありますよ。
例えば、次のような簡単なアクションを心がけてみましょう:
- 席を立って用件を伝える: 社内での用事はメールや内線で済ませず、相手のデスクまで歩いて行って直接話すようにする。ちょっとした移動でも積み重ねれば良い運動になります。
- こまめに席を離れる: 書類のプリントやコピーを一度にまとめず、こまめに取りに行く習慣をつけましょう。給茶や給水も適度に行えば、水分補給とリフレッシュを兼ねられます。
- スタンディングワークを活用: 可能であれば高さ調節できる昇降式デスクを使い、時々立って作業すると座り時間を減らせます。また電話対応の時だけでも立って話すようにすると、自然と立つ機会が増えます。
- 立ってミーティング: 短時間の打ち合わせや朝礼などは椅子を使わず立ったまま行うのも一法です。立って話すと会議自体の効率も上がるという声もあります。
- リマインダーを活用: スマホやPCのアプリで「○○分ごとに立ち上がる」と通知を出したり、タイマーで作業時間を区切ったりして、意識的に休憩タイムを入れましょう。
こうしたちょっとした工夫で、「気がついたら何時間も座りっぱなしだった!」という状況を防ぐことができます。実際、30分に一度立ち上がって体を動かす習慣を取り入れた人は、全く休憩を入れず座り続けた人に比べて血糖値など健康指標が改善するというデータもあります。ある実験では、30分ごとに3分間の休憩を入れるグループは、ずっと座っていたグループに比べて血糖値の上昇が20%も抑えられたそうです。短い休憩でもこまめに入れれば、運動強度にかかわらず健康に良い効果が出るというのは嬉しいですね。
「それでも仕事中になかなか立てない…」という方もいるでしょう。例えばコールセンターや運転手のように業務の特性上席を離れにくい場合もありますよね。そんな時は、座ったままできるエクササイズで血行を促しましょう。おすすめはかかとの上げ下ろし運動や足首の曲げ伸ばしです。デスク下でつま先立ち・かかと下ろしを繰り返したり、足首をグルグル回したりするだけでもふくらはぎの筋肉がポンプ代わりになり、血液循環が良くなります。これはエコノミークラス症候群の予防策としても知られており、長時間フライトだけでなくオフィスでも応用できます。さらに椅子に座ったまま肩をゆっくり回したり、首を傾けてストレッチしたりと、上半身の軽い体操をするのも効果的です。周囲に気付かれずこっそりできるストレッチでも、やらないより断然マシですよ。
また、勤務中以外の時間にも目を向けてみましょう。例えば帰宅後や休日に適度な運動習慣を持つことも大切です。「平日は座りっぱなしだけど週末にまとめて運動しているから大丈夫!」という声もありますが、残念ながら座りすぎのリスクを帳消しにするには週末だけでは不十分です。ある研究では、座りすぎによる健康への悪影響を打ち消すには1日60分以上の運動が必要だと示唆されています。つまり「運動不足の解消」と「座りすぎの解消」は別問題と考え、平日もできる範囲で体を動かす機会を作ることが重要なのです。
最後に、職場全体で取り組む工夫もご紹介します。最近では従業員の健康づくりの一環として、**「健康経営」**の観点から座りすぎ対策に力を入れる企業も増えてきました。たとえば毎正時(毎時間ちょうど)になると音楽が流れ、社員全員が40秒ほど席の周りを歩くルールを設けている会社や、1日3回・各3分間社員全員でストレッチをする時間を設定している職場もあるそうです。他にも、始業前にラジオ体操を取り入れたり、バランスボールを椅子代わりに使って体幹を鍛えたりとユニークな取り組みも報告されています。こうした工夫は社員の皆さんにとってもリフレッシュになりますし、結果的に生産性向上やチームのコミュニケーション活性化にもつながるようです。ぜひ皆さんの職場でもできそうなことから試してみてくださいね。
⑤ まとめ
長時間座りっぱなしの生活が、私たちの体と心の健康にさまざまなリスクをもたらすことがお分かりいただけたでしょうか。デスク上でほとんどの仕事が完結してしまう便利な時代だからこそ、意識して体を動かさないとどんどん「座りすぎ」になってしまいます。特にオフィスワーカーの皆さんは、自分の生活を振り返って「もしかして座りすぎかも?」と思ったら、まずは1時間に一度立ち上がることから始めてみましょう。ほんの数分体を動かすだけでも、血行が促されて眠気やだるさがスッキリし、仕事への集中力も高まりますよ。
健康維持のための対策は、継続してこそ効果が出るものです。最初は面倒に感じるかもしれませんが、タイマーをセットするなど工夫して習慣化してみてください。周囲を巻き込んで職場全体で取り組めれば理想的ですし、自分一人でも「ながらストレッチ」などできることはたくさんあります。運動不足も座りすぎも少しずつ解消していけば、きっと体調が整い気持ちも前向きになるはずです。今日からぜひ、**「ちょこちょこ立つ・動く」**を合言葉に、快適で健康的なオフィスライフを送ってくださいね。


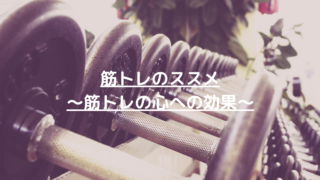



コメント