
目 次
① はじめに
日本の夏は高温多湿で、寝室やリビングがジメジメしがちです。湿度が高いと汗が乾きにくく不快に感じるだけでなく、カビやダニなどの発生リスクも高まります。カビは壁や家具を傷めるだけでなく、健康被害(アレルギーや喘息など)を引き起こす可能性もあるため、湿気対策はとても重要です。とはいえ、本格的な除湿機を購入するとなると費用やスペースの問題がありますよね。そこで本記事では、除湿機を買わずにできる湿気対策のアイデアを紹介します。一般的な湿気対策のポイントから、誰でも手軽に試せる除湿機の代用品まで、再現性・コスト・手軽さを踏まえて解説します。ジメジメした梅雨~夏の時期を少しでも快適に乗り切るために、ぜひ参考にしてください。

毎日ジメジメ、、
☑︎除湿機を買うほどではないけど湿気対策をしたい方
☑︎賃貸や一時的な住環境で除湿器を置きにくい方
☑︎DIYや身近なもので快適な室内環境を作りたい方
② 除湿対策(一般的な湿気対策の知識と手法)
湿気対策の基本は換気と風通しです。室内の湿った空気を外に逃がし、新鮮な乾いた空気と入れ替えることで湿度を下げます。晴れて乾燥している日は朝夕に窓を開けて数分換気し、空気の入れ替えを習慣にしましょう。部屋の対角線上に2か所の窓を開けると風の通り道ができ、効率よく換気できます。窓が一つしかない部屋では扇風機やサーキュレーターで空気を循環させ、換気扇を併用すると効果的です。
湿気は家のさまざまな場所から発生します。例えば浴室は大量の水蒸気が出るので、お風呂上がりには冷水シャワーで壁面を冷やしたり、水滴をしっかり拭き取ってから換気扇を回すと良いでしょう。室内干しの洗濯物も室内湿度を急上昇させます。可能な限り洗濯物は屋外に干すか、浴室乾燥機を使い、どうしても部屋干しする場合はエアコンの除湿(ドライ)機能を併用してください。また、観葉植物や水槽は意外な湿気源になります。植物への水やりや水槽の蒸発で部屋の湿度が上がるため、湿気が気になる部屋では数を減らすことも検討しましょう。
基本的な湿気対策として、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 定期的に換気する:晴れた日は窓を開け放ち、湿った空気を外へ。難しい場合は換気扇を回す。クローゼットや押し入れも扉を開けて空気を入れ替えると◎。
- 風の通り道をつくる:大型家具は壁から少し離して配置し、背後に空気が流れる隙間を確保します。空気が滞留しがちな箇所は小型ファンで循環させましょう。
- 結露を放置しない:夏場でも冷房で室内外温度差が大きいと窓に結露します。窓ガラスやサッシの水滴は見つけ次第拭き取り、溜めないようにします。窓に断熱シートを貼る等の結露対策も有効です。
- 湿度の高いものを室内に持ち込まない:洗濯物の室内干しは最小限に。布団は晴れ間に干すか布団乾燥機で乾燥を。観葉植物・水槽も必要以上に置かないようにします。
- 湿度計を設置する:快適な室内湿度は**40~60%**程度と言われます。湿度計を置いてこまめにチェックし、梅雨時や夏場は常に60%以下を目指しましょう。湿度が高すぎる時はエアコン除湿機能や除湿剤で下げてください。
これらの基本対策に加え、次章では除湿機の代わりになる具体的な方法を紹介します。電気を使わないエコな工夫や身近なアイテムを活用したテクニックで、コストを抑えながら効果的に湿度をコントロールしてみましょう。
③ 除湿機の代わりになるもの

一般的な換気やエアコン以外にも、工夫次第で室内の湿気を和らげる方法がいろいろあります。ここでは除湿機を使わずにできる具体的な除湿テクニックをいくつかご紹介します。それぞれ再現性(誰でも実践可能か)、コスト、手軽さの面からメリット・デメリットがありますので、併せて解説します。
市販の除湿剤(湿気取り)を使う
ドラッグストアやホームセンターで売られている除湿剤(湿気取り)を活用する方法です。代表的なものはプラスチック容器に入った塩化カルシウム系の除湿剤で、「水とりぞうさん」「ドライペット」などの商品名で親しまれています。数百円程度で購入でき、容器のフタを開けて設置しておくだけで空気中の余分な湿気を吸収し、容器内に水(塩化カルシウムが吸収した水分)が溜まっていきます。交換の目安は数ヶ月おき(満水になったら)で、使い捨てタイプが一般的ですが、中には天日干しで再利用できるタイプもあります。比較的コストも安く手に入り、誰でもすぐ実践できる手軽さが魅力です。
設置場所のポイントは湿気がたまりやすい場所の下部です。湿った空気は重いため下にたまりがちなので、押し入れなら下段の床、クローゼットなら床に近い位置に置くと効果的です。容量は設置場所の広さに応じて選びましょう。クローゼットなど狭い空間には吊り下げ型やシート型の除湿剤も便利です。これらは衣類の間に掛けたり引き出しに敷いたりして使え、除湿と同時に消臭効果を備えた製品もあります。
メリット: 専用品だけあって除湿効果は高く、手軽に設置できる点が最大のメリットです。価格も1個あたり100円~300円程度と安価で、複数買って家中に置いても大きな負担になりません。湿気をしっかり水に変えて「見える化」してくれるので達成感もあります。
デメリット: 廊下や広いリビングなど広い空間では即効性がやや劣る点です。除湿剤1個でカバーできる範囲はせいぜい数畳程度なので、部屋全体の湿度を大きく下げるには限界があります。また、定期的に交換が必要で、水が満杯になった容器を廃棄する手間があります(※塩化カルシウム水溶液は排水口に流すと金属を腐食させる恐れがあるため注意事項を守って処分しましょう)。とはいえ**「湿気取り」は手軽さ・安さ・効果のバランスが優れたおすすめの方法**です。
炭や調湿グッズを使う
**炭(竹炭や備長炭など)**には湿度を調節する働きと消臭効果があります。炭の内部に無数の細かい穴があり、水分や臭い成分を吸着してくれるため、昔から下駄箱や押し入れの防臭・除湿に活用されてきました。市販の調湿グッズとして、炭を不織布で包んだパックや炭を練り込んだ調湿シート・ボードなども販売されています。例えば、炭を原料とした繰り返し使える除湿剤「炭八(すみはち)」は代表的な製品で、大袋1つで広めの空間の湿気を吸収し、天日干しすれば何度も再利用可能です。調湿シートは押し入れやベッド下に敷くだけで湿気を吸い取ってくれ、干せば繰り返し使えるものが多いです。
メリット: 炭や調湿シートは半永久的に使えるものが多く経済的です。一定量の湿度を吸うと飽和しますが、陰干し・天日干しすることで再び乾燥させて繰り返し使える点が魅力です。電気も使わず静かに湿度調節してくれるので、クローゼットや寝室などで24時間稼働させておきたい場合にも安心です。消臭効果もあるため、下駄箱や押し入れのこもった臭い対策にも一石二鳥です。
デメリット: 即効性という点では化学系の除湿剤や除湿機ほど強力ではありません。炭は湿度を急激に下げるというより、高湿時に水分を吸収し乾燥時に放出する調湿役といった性格です。広いリビングなどで劇的に湿度を下げるのは難しく、効果は緩やかと考えましょう。また、市販の炭グッズは除湿剤より価格が高めです(炭八の場合、大袋1個で数千円程度)。とはいえ繰り返し使えることを考えれば長期的にはコスパ良好です。なおBBQ用の木炭は崩れやすく粉が出て不向きなので、除湿用途には市販の調湿用炭を選ぶようにしましょう。
新聞紙や重曹など身近なもので湿気対策
特別なグッズがなくても、家にある身近なもので湿気を取る方法があります。代表格は新聞紙です。新聞紙は繊維が粗くて吸湿性が高く、水分をぐんぐん吸い込んでくれます。押し入れや靴箱の底に新聞紙を敷いたり、クシャクシャに丸めて隙間に詰めたりするだけでも湿気取りに効果があります。例えば「洗濯物の室内干しの下に新聞紙を敷いておくと、かなり湿気を取ってくれる」という声もあり、濡れた靴の中に新聞紙を詰めて乾かすのは定番のテクニックです。新聞紙はほぼタダで使い捨てでき、湿気と同時にホコリや汚れもキャッチしてくれるので、一石二鳥でもあります。数日使用して湿ってきたら、新しい紙に交換するだけなのでお掃除代わりにもなります。
また、キッチンにある重曹(炭酸水素ナトリウム)も簡易除湿剤として活躍します。重曹は粉末状で多孔質な構造をしており、湿気と臭いを吸着する性質があります。不織布やガーゼの袋に重曹を入れて口を縛れば、クローゼットに吊るして使える手作り除湿剤の完成です。瓶やカップに重曹を入れて置いておくだけでもOK。しばらく使って湿気を吸った重曹は、捨てずにそのままクレンザー代わりに掃除に再利用できるのも嬉しいポイントです。粉末の洗濯用洗剤も同様に湿気を吸うので、フタを開けてクローゼットに置いておくという裏ワザもあります(※湿気を吸った洗剤は本来の洗浄力が落ちる可能性もあるため、使用期限内に洗濯で使い切りましょう)。
メリット: 新聞紙や重曹は手元にあるものですぐ試せてコストがほぼゼロなのが最大のメリットです。使い終わった後も掃除に流用できたり、そのまま処分できたりと手軽です。特に新聞紙は大量に使っても惜しくないので、部屋のあちこちに敷き詰めて思い切った除湿ができます。
デメリット: 吸湿力は緩やかで、梅雨時や真夏など湿度が高すぎる環境では追いつかない場合があります。新聞紙は見た目が悪く部屋の美観を損ねる点も難点です。重曹や洗剤も、小さな容器1つでは吸える湿気量は限定的で、広範囲の湿度を下げるのは難しいでしょう。ただし**「塵も積もれば山となる」**という言葉通り、捨てるはずのものを活用して少しでも湿度を下げられるのは有益です。新聞紙に至ってはホコリ取り効果も兼ねられるので、他の方法と併用しつつ定期的に交換することで、湿気と汚れをまとめて除去でき一石二鳥です。
凍らせたペットボトルを置く
「凍らせたペットボトルを部屋に置くと除湿できる」というライフハックがSNSで話題になったことがあります。凍ったペットボトルは周囲の空気を冷やし、その空気中の水分がボトル表面で結露(水滴)となって現れます。この結露分だけ空気中の湿気が減るため、「エアコンの除湿機能の代わりになるのでは?」と注目されたわけです。実際にコップの周りに水滴が付く現象を思い浮かべればイメージしやすいでしょう。やり方は簡単で、ペットボトルに水を入れて凍らせ、受け皿(ボウル等)に入れて室内に置くだけです。
しかし結論から言うと、この方法だけで部屋全体をカラッとさせるのは難しく、除湿効果は限定的です。例えば2.5リットル分の冷凍ペットボトルを一晩(約8時間)置いた場合で、容器に溜まった水は約80ml程度でした。大さじ5杯強ほどの水分が空気中から除去できた計算ですが、エアコン除湿と比べると微々たる量です。また、氷が溶けきってしまうとそれ以上の除湿はできず、長時間続けるには途中でボトルを交換・再冷凍する手間もかかります。
メリット: 電気代ゼロで誰でもすぐ試せる点がメリットです。冷凍庫にペットボトルの氷をストックしておけば、停電時や扇風機だけでは暑い夜などに応急処置的に湿度を下げる効果は期待できます。実際に「扇風機の風がほんのり冷たくなり、結露した水が目に見えるので気休めには上々だった」という体験談もあります。エアコンの除湿機能を弱めに設定しておき、補助的にペットボトル除湿を併用すれば多少の節電にはつながるでしょう。
デメリット: 前述の通り、単独で部屋の湿度を大幅ダウンさせるほどの効果は望めません。冷凍庫の空き容量も必要ですし、床に水滴が落ちないようタオルを敷くなどの配慮も必要です。氷が溶けた後の後片付けも意外と手間がかかります。また、ボトル周辺しか空気が冷えないため、部屋全体の温度・湿度を快適にするには数本では焼け石に水です。結論として、ペットボトル除湿はあくまで「ちょっとした豆知識」的な補助策であり、過度な期待は禁物です。エアコンや除湿剤を使いつつ、「塵も積もれば」で併用するのが現実的と言えるでしょう。
④ まとめ
以上、除湿機を使わずにできる湿気対策のポイントと代用品をご紹介しました。最後に各方法の再現性・コスト・手軽さ・おすすめ度を比較表にまとめます。ご自身の環境や予算に合わせて、取り入れやすい方法から試してみてください。
| 方法 | 再現性(誰でもできる度) | コスト | 手軽さ | おすすめ度(効果) |
|---|---|---|---|---|
| 市販の除湿剤 | ◎(入手容易) | ◎(安価) | ◎(置くだけ) | ◎ (定番おすすめ) |
| 炭・調湿グッズ | ○(入手容易) | ○(やや高め) | ○(設置・陰干し) | ○ (緩やかに効く) |
| 新聞紙・重曹など身近品 | ◎(今すぐ可能) | ◎(ほぼ無料) | ○(交換必要) | △ (補助として) |
| 冷凍ペットボトル | ◎(今すぐ可能) | ◎(無料同然) | △(準備手間) | △ (効果少なめ) |
※「再現性」はその方法が特別な道具・技術なしに誰でも実践できるか、「コスト」は必要経費の大小、「手軽さ」は準備やメンテナンスの手間、「おすすめ度」は筆者の主観による総合評価です。「◎」は特に優れている、「○」は概ね良好、「△」はやや劣ることを示しています。
ご覧のように、即効性や強力な除湿力では電気式の除湿機やエアコンに軍配が上がりますが、身近な工夫を組み合わせることでかなり湿気対策は可能です。まずは換気や生活動線の見直しなど基本対策を行った上で、市販グッズや手作り除湿剤を活用してみましょう。特に押し入れ・クローゼット・下駄箱など密閉空間の湿気対策には除湿剤や炭が効果的です。一方、リビングや寝室など広い空間では、扇風機+除湿剤+新聞紙、と複数の方法を併用することでじわじわと効果が出てきます。費用をかけず工夫次第で湿度はコントロールできますので、ぜひ今回紹介した代用品を試してみてください。じめじめした夏場でも、ちょっとした工夫で快適で健康的な住環境を保ちましょう!


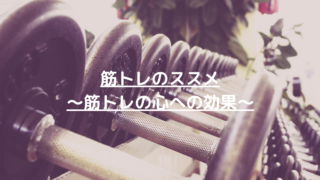


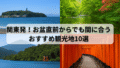

コメント