目 次
① はじめに
「ワインってちょっと難しそう…」そんなふうに感じていませんか?実はワインの世界は、ほんの少しポイントを知るだけでぐっと身近で楽しいものになるんです。赤ワインと白ワインの違いや、おいしい飲み方、料理との組み合わせなど、基礎からていねいにお話ししていきます。堅苦しい専門用語はできるだけかみ砕いて、親しみやすい言葉で説明するのでご安心ください。初心者の方でもこの記事を読み終える頃には、きっと自分に合ったワインの選び方や楽しみ方がわかるはずですよ。
それでは、さっそくワインの魅力を一緒に探っていきましょう!

ワインって敷居が高いイメージ
☑︎ワイン初心者で「何を選べばいいか分からない」方
☑︎料理とワインの相性に興味がある方
☑︎お店や酒屋でワインを自分で選びたい方
② 赤ワインの代表的な国とブドウの品種

まずは赤ワインから見ていきましょう。赤ワインは世界中のさまざまな国で造られており、それぞれの産地で代表的なブドウ品種があります。特に有名なのがフランスやイタリア、スペインといったヨーロッパの国々です。フランスのボルドー地方ではカベルネ・ソーヴィニヨンやメルローといった品種が使われ、力強くコクのある赤ワインが生み出されています。またブルゴーニュ地方では繊細な味わいのピノ・ノワールが主役です。イタリアに目を向けると、トスカーナ地方のサンジョベーゼ(有名なキアンティの原料)や、北部ピエモンテ地方のネッビオーロ(バローロなどの高級ワインに使用)などが挙げられます。スペインならば、リオハ地方のテンプラニーリョが代表的ですね。
欧米以外でも、高品質な赤ワインを産出する国があります。たとえばアメリカのカリフォルニア州(ナパ・ヴァレーなど)はボルドー系品種のカベルネ・ソーヴィニヨンやメルローで有名ですし、オーストラリアではシラーズ(シラー)という品種から果実味たっぷりの赤ワインが造られています。近年はチリやアルゼンチンといった南米のワインも人気で、チリのカルメネールやアルゼンチンのマルベックなど、その土地ならではのブドウが注目されています。
このように、赤ワインは産地ごとに主に使われるブドウ品種が異なり、それがワインの個性につながっています。もちろんフランスやイタリアのブドウが他国でも栽培されていたり、複数の品種をブレンドしているワインもありますが、まずは**「どの国のどんなブドウから造られたワインか」**を意識してみると、選ぶときの手がかりになりますよ。
③ 白ワインの代表的な国とブドウの品種
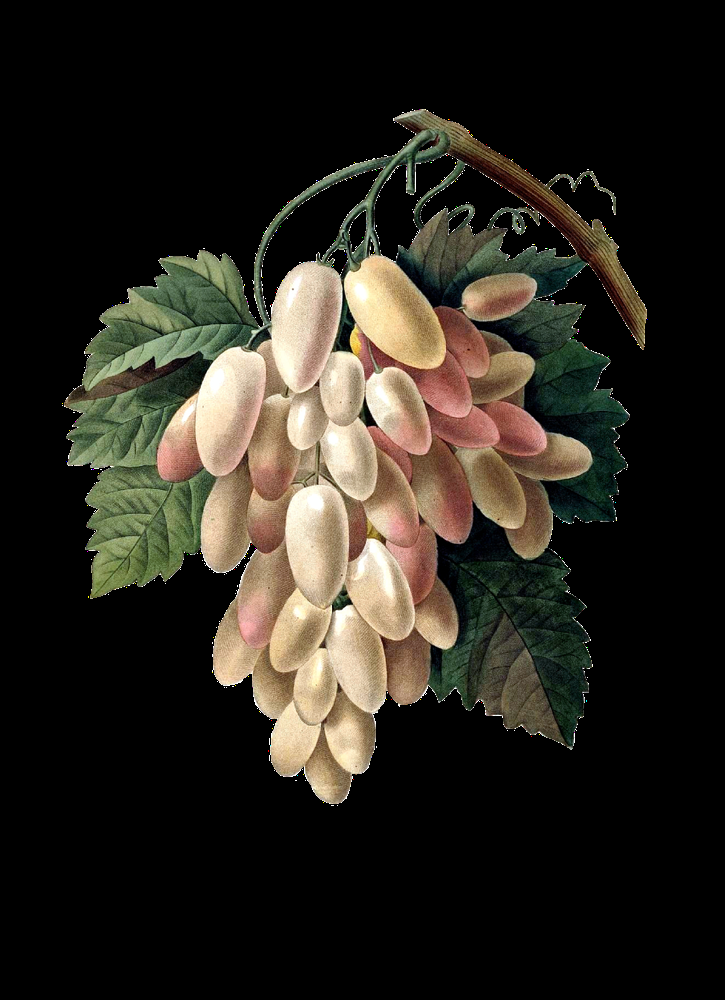
次に白ワインについて見てみましょう。白ワインもまた世界各地で造られ、多彩なブドウ品種が使われています。白ワインといえばまずシャルドネを思い浮かべる方が多いかもしれません。フランスのブルゴーニュ地方の白ワイン用ブドウとして有名で、世界中ほぼどこでも栽培されるほど適応力のある品種です。シャルドネから造られるワインは産地や造り手によって味わいが大きく変わり、コクのある樽熟成タイプから爽やかな辛口まで幅広いスタイルがあります。
シャルドネに並んで代表的なのがソーヴィニヨン・ブランです。フランスのロワール地方やボルドー地方で知られますが、ニュージーランド産のソーヴィニヨン・ブラン(例えばマールボロ地区のもの)は特に有名で、青草やハーブを思わせる爽やかな香りが特徴です。またドイツを代表する白ワイン用品種としてリースリングも欠かせません。リースリングは酸味がしっかりとしており、辛口から甘口まで幅広いタイプのワインが造られます。桃やリンゴのようなフルーティーな香りが楽しめ、ドイツやアルザス(フランス)、オーストラリアなどで高品質なリースリングワインが生み出されています。
その他にも個性的な白ブドウ品種があります。イタリアではピノ・グリージョ(フランス名ピノ・グリ)が有名で、軽やかで飲みやすい白ワインになることが多いです。スペインのアルバリーニョやドイツ・フランスで造られるゲヴュルツトラミネールは華やかな香りを持つ品種として知られます。また、日本にも白ワイン用の固有品種として甲州というブドウがあり、山梨県を中心にさっぱりとした和食に合う白ワインが造られています。
このように、白ワインも産地ごとに**「この土地ならではのブドウ」**があります。ラベルを見るとブドウ品種が書かれているワインも多いので、最初はシャルドネやソーヴィニヨン・ブランなど知っている品種名を目安に選ぶと、自分の好みに合った白ワインに出会いやすいでしょう。
④ それぞれのテイストの特徴

赤ワインと白ワインでは色だけでなく味わいの傾向も大きく異なります。まず赤ワインは、渋みのもととなるタンニンという成分を多く含む点が特徴です。タンニンはブドウの皮や種に由来し、赤ワイン造りでは果皮も一緒に発酵させるため渋みが溶け込むのです。このタンニンが多いほど、味わいに渋みとコクが増し「重たい(フルボディ)」と感じられるワインになります。例えばカベルネ・ソーヴィニヨン主体のワインはタンニンが豊富でしっかりとした渋みがあります。一方でライトボディと呼ばれる軽やかな赤ワイン(ピノ・ノワールなど)はタンニンが穏やかで口当たりが柔らかく、渋みが苦手な方でも飲みやすいでしょう。
白ワインの場合、基本的にタンニンはほとんど感じられません。その代わり酸味が味わいの骨格になります。キリッとした酸味のおかげで白ワインは爽やかでスッキリとした飲み心地のものが多いです。ソーヴィニヨン・ブランなどは特に酸味がはっきりとしており、「辛口ですっきり」「フルーティーで爽やか」といった表現がぴったりです。ただし、シャルドネのように産地や醸造方法によっては樽熟成でコクが加わり、まろやかな味わいになる白ワインもあります。白ワインには甘口のデザートワインも存在しますが、初心者の方はまず辛口ですっきりタイプから試すのがおすすめです。
また、赤白に共通するポイントとしてボディ(コクの重さ)と甘辛(甘口か辛口か)があります。ボディは「重い⇔軽い」という表現で、アルコール度数や味の濃さのニュアンスです。フルボディの赤ワインは濃厚で飲みごたえがありますし、ライトボディならばさらっと飲めます。白ワインでもコクのあるものは「ふくよかな味わい」と表現されたりしますね。そして甘口・辛口ですが、ワインでは一般に辛口=甘くないドライな味を指します。ほとんどのテーブルワインは辛口ですが、中には果実の自然な甘さを生かした甘口ワインもあります。甘口ワインはアルコール度数が低めでデザート感覚で飲めるので、お酒が苦手な方でも楽しみやすいですよ。
このように、赤ワインは渋みとコク、白ワインは酸味と爽やかさが持ち味となります。ただ実際には品種や造り方で例外も多く、一概に決めつけられません。例えば薄い色の赤ワインは冷やして飲むと爽やかに感じたり、コクのあるオレンジワイン(白ブドウを皮ごと発酵させたワイン)は渋みもあったりします。ですから、**「赤だからこう、白だからこう」**と深く考えすぎず、「この赤はこういう味」「この白はこういう香り」というふうに一本一本向き合ってみると、ワインのテイストをより楽しめるでしょう。
⑤ ワインと食べ物のペアリングの楽しみ方

ワインの醍醐味のひとつに、料理とのペアリング(組み合わせ)があります。難しく考える必要はありませんが、上手に組み合わせると**「ワインも料理もさらに美味しくなる」**という嬉しい効果があります。基本的なペアリングの考え方としては、味の重さを合わせることが挙げられます。これはつまり、濃厚でしっかりした味の料理には重めのコクのあるワイン、あっさりした料理には軽めで爽やかなワインを合わせるということです。例えば、ステーキやローストビーフなどボリュームのある肉料理にはフルボディの赤ワイン(カベルネ・ソーヴィニヨンなど)を合わせると、お互いの風味がバランスよく調和します。逆に繊細な白身魚のムニエルやサラダには軽やかな白ワイン(ピノ・グリージョやソーヴィニヨン・ブランなど)が爽やかさを添えてくれるでしょう。
もう一つのポイントは、香りや風味の共通点・対比を活かすことです。同じような香りや風味を持つ組み合わせは相性が良いと言われます。例えば、樽熟成したシャルドネにはバターやナッツのような香ばしさがありますが、クリーム系のソースを使った鶏肉料理やキノコのバター炒めなどと合わせると風味が見事にマッチします。また、対照的な組み合わせも面白く、甘口ワインと塩気のあるチーズはその代表です。濃厚な青カビチーズに極甘口の貴腐ワインを合わせると、塩味と甘味がぶつかり合いながらも不思議と調和して、まるでデザートのような絶妙なハーモニーを生み出します。
日本食とのペアリングもぜひ挑戦してみてください。魚の刺身やお寿司にはキリッと冷えた辛口の白ワインがさっぱりとして相性抜群ですし、照り焼きやすき焼きのような甘辛い味付けの料理にはフルーティーな赤ワイン(ライトボディ寄り)が合うことがあります。「ワインにはチーズや洋食じゃなきゃダメ」ということは全くありません。最近では和食に合わせたワイン選びも提案されており、たとえば天ぷらとシャンパン(スパークリングワイン)の組み合わせは油を爽やかに流してくれる黄金ペアです。
ペアリングの世界は本当に奥深いですが、一番大切なのは自分がおいしいと感じる組み合わせです。セオリーに縛られすぎず、「このワインには何を食べようかな?」とワクワクしながら自由に試してみてください。ワインと食べ物がお互いを引き立て合う経験をすると、食卓がもっと楽しくなりますよ。
⑥ 各ワインの品種、味の特徴、ペアリングの早見表
ワイン選びやペアリングの参考に、主要なブドウ品種の特徴と相性の良い料理をまとめました。赤ワインと白ワインそれぞれ代表的な品種をピックアップしています。初心者の方でもイメージしやすいように簡潔にまとめたので、ぜひ活用してください。
| ブドウ品種(色) | 味わいの特徴 | 相性の良い料理や食材 |
|---|---|---|
| カベルネ・ソーヴィニヨン(赤) | フルボディで渋みが強く、カシスのような濃い果実味。重厚感あり | ステーキ、ラムチョップなど赤身肉料理、デミグラス系ソースの料理 |
| ピノ・ノワール(赤) | ライト~ミディアムボディ。酸味が程よく、チェリーのような赤い果実の香り。渋みは穏やか | 鴨のロースト、マグロのグリル、キノコ料理(和風の照り焼きとも好相性) |
| メルロー(赤) | ミディアムボディ。渋みはまろやかで、プラムのような柔らかな果実味が豊か | ハンバーグ、ミートパスタ、豚の生姜焼きなどコクが中程度の肉料理 |
| シャルドネ(白) | ミディアム~フルボディ。産地によるが、樽熟成タイプはバターやバニラの風味でコクあり、非樽熟成は柑橘系で爽やか | シーフードグラタン、クリームシチュー、ローストチキン、クリーム系パスタ |
| ソーヴィニヨン・ブラン(白) | ライト~ミディアムボディ。高い酸味とハーブや青りんごのような爽やかな香り。辛口 | 白身魚のカルパッチョ、山羊のチーズ、グリーンサラダ、天ぷら |
| リースリング(白) | ライトボディ。酸味がしっかりしフローラルな香り。産地で辛口~甘口まで様々だがフルーティ | エスニック料理や辛い料理(半甘口なら)、豚肉のソテー、寿司(辛口なら) |
| (参考)スパークリングワイン | 泡による爽快感。白・ロゼあり、辛口が主流。シャンパンはコクも備える | 食前酒に最適。フライドチキンやポテトチップスとも◎(油を洗い流す効果) |
※上記の「色」は【赤】=赤ワイン用黒ブドウ品種、【白】=白ワイン用ブドウ品種を示しています。同じ品種でも産地や作り手によって味わいは異なりますが、一般的な傾向をまとめました。
早見表を見ると、「この料理にはこのワインが合いそうだな」とイメージしやすくなったのではないでしょうか。もちろん個人の好みやその時々の調理法によってベストマッチは変わります。あくまで目安として参考にしつつ、実際にいろいろ試しながら自分なりのペアリングを発見してみてくださいね。
⑦ 店で選ぶ時のポイント

いよいよ実践編、お店でワインを選ぶ際のポイントです。レストランでワインを注文する場合と、ワインショップで自分でボトルを選ぶ場合とで少し状況が異なりますが、まずはレストランなどでのケースを考えてみましょう。レストランでワインリストを手にしたとき、「どれを選べばいいんだろう…」と迷うのは当然です。でも安心してください。お店には頼れるソムリエやワインに詳しいスタッフがいる場合が多いので、ぜひ積極的に相談してみましょう。例えば「赤ワインが飲みたいけど、重すぎないものが好みです」とか「魚料理に合う白ワインを探しています」といった具合に、自分のざっくりとした希望を伝えるだけでOKです。プロはあなたの予算や料理に合わせてピッタリの一本を提案してくれるはずです。
もし「相談するのはちょっと恥ずかしい…」という場合でも、メニューに書かれたワインの説明文を手がかりにしましょう。最近はワインリストに「フルボディ」「ミディアムボディ」や「柑橘系の香り」「タンニンしっかり」など簡単な特徴が書かれていることもあります。またグラスワイン(1杯単位で注文できるもの)があるなら、初心者の方はまずグラスで頼んでみるのも良いですね。ボトル1本より気軽に色々試せますし、好みじゃなかった…というリスクも少なくて済みます。
レストランでソムリエから「重めがよろしいですか?軽めがよろしいですか?」などと聞かれることがあります。これは単にボディ(コク)の強さを尋ねているので、わからなければ正直に「違いがよく分からないのでお任せします」と言ってしまって大丈夫です。感じ方は人それぞれですから、プロに任せてしまいましょう。また、ボトルを注文した際は最初に少量注いでくれるテイスティングがあります。難しい儀式ではなく、明らかに劣化していないか確認するためのものなので、ひと口飲んで「問題ありません」と微笑めばOKです。肩肘張らず、せっかくの食事とワインをリラックスして楽しんでくださいね。
⑧ 店頭で購入するときのポイント
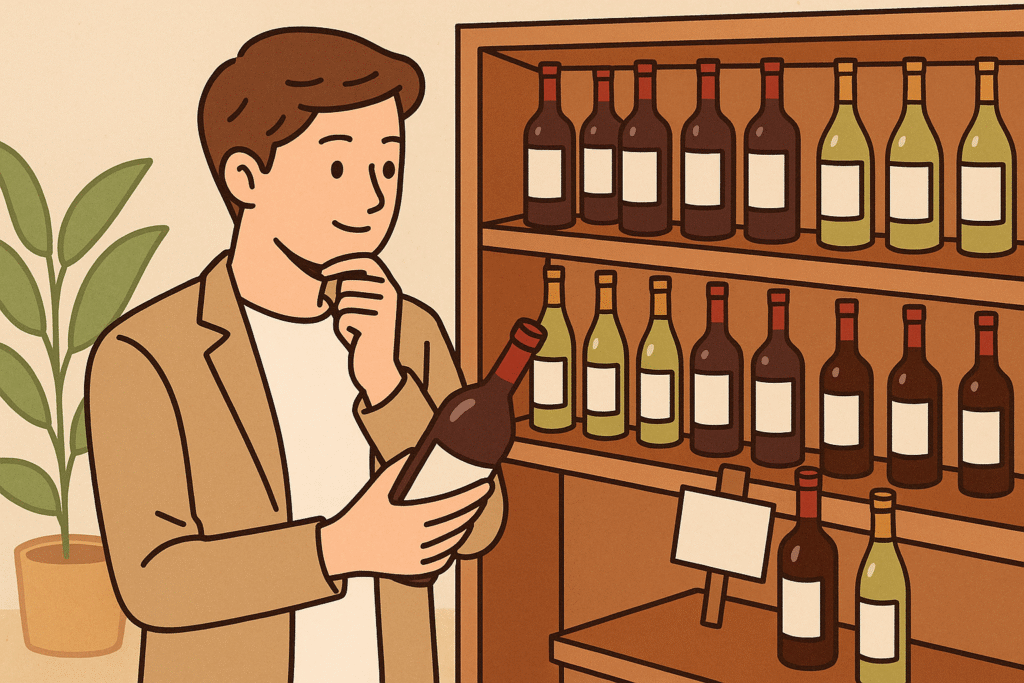
次に、ワインショップや酒屋さんでボトルを購入する際のポイントをお伝えします。お店の棚には世界各国のワインがずらりと並び、最初は圧倒されるかもしれません。そんなとき役立つのがこの記事の前半でお話しした知識です。ラベル(エチケット)に注目してみましょう。大抵ラベルには産地やブドウ品種、ヴィンテージ(葡萄の収穫年)が記載されています。もし好きな産地や品種が頭に浮かぶなら、その名前を探してみてください(例えば「フランス・ボルドー」「カベルネ・ソーヴィニヨン」など)。新世界(チリやオーストラリアなど)のワインは品種名が大きく表示されていることが多いので選びやすいですよ。
また、お店でボトルを手に取ったら裏ラベルの日本語解説も読んでみましょう。味わいの目安(辛口~甘口の度合いやボディ表示)がグラフで示されていたり、「○○や△△の香り、滑らかな口当たり」といったコメントが書かれていたりします。専門用語が並んでいるときは無理に全部理解しようとしなくても大丈夫です。「このワインはどんな雰囲気なのかな?」と想像するヒントとして眺めてみてください。
ワインショップの店員さんもソムリエ同様に頼れる存在です。遠慮なく「初心者なんですが、予算○○円くらいで飲みやすいワインはありますか?」と尋ねてみましょう。好みがわからない場合は、「フルーティーな感じが好き」「渋いのは苦手かも」といったざっくりした伝え方でも十分です。プロは豊富な知識の中からあなたに合いそうな一本を選んでくれるでしょう。特に専門店では試飲イベントを開催していたり、おすすめPOPが貼ってあったりしますので活用してください。
最後に、店頭でボトルを購入するとき覚えておきたい小ネタをいくつか。まずワインは振動や高温に弱いので、夏場に買った後はできるだけ早く涼しい場所に保管しましょう(長時間車内に放置はNGです)。持ち運び時に瓶を強く振らないよう気をつける程度でOKです。また、スクリューキャップのワインなら栓抜き不要ですぐ開けられますが、コルク栓のワインを買うときはワインオープナーも用意しておきましょう。「せっかく買ったのに開けられない!」となったら悲しいですものね。もしお家にワイングラスが無ければ、この機会に揃えてみるのもおすすめです。最近は100円ショップでも手頃なワイングラスが手に入ります。
店頭でのワイン選びに決まりごとはありません。ラベルのデザインや産地名に惹かれて選ぶのも立派な理由です。「なんだか難しそうだな」と感じたら、予算内で一番気になるボトルを直感で買ってみるのもアリですよ。それも経験のうち、開けて飲んでみれば新たな発見があるはずです。
⑨ まとめ
ここまで、ワインの基本から選び方・楽しみ方のコツまで幅広くご紹介しました。難しそうに思えたワインの世界も、ポイントさえ掴めば決して敷居が高くないことがお分かりいただけたのではないでしょうか。赤ワインと白ワインの味わいの違いや、代表的なブドウ品種と産地の話を知ることで、ラベルを見たときの手がかりが増えます。また、料理とのペアリングはワインをもっと美味しくしてくれる楽しい工夫です。「この料理にはこれ!」と完璧に合わせる必要はなく、ぜひ自由な発想でいろいろ試してみてください。
ワイン選びに正解はありません。一番大切なのは、「自分がおいしいと思えるワイン」に出会うことです。そのためにはとにかくチャレンジあるのみ。初心者のうちはわからないことだらけで当然ですから、本記事の内容を参考にしつつ、気軽にいろんなワインを味わってみてください。飲んだワインの名前や感想をメモしておくと、自分の好みが見えてきておすすめですよ。
最後に、ワインはお酒ですので適量を守って楽しく嗜みましょう。ゆったりとグラスを傾けながら、自分のペースでワインライフを満喫してくださいね。「難しい」より「おいしい!」「楽しい!」が増えていけば何よりです。それでは乾杯!あなたのワインのある生活が素敵なものになりますように。


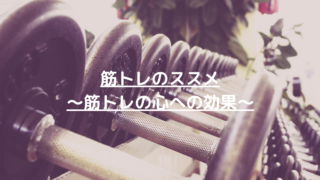




コメント